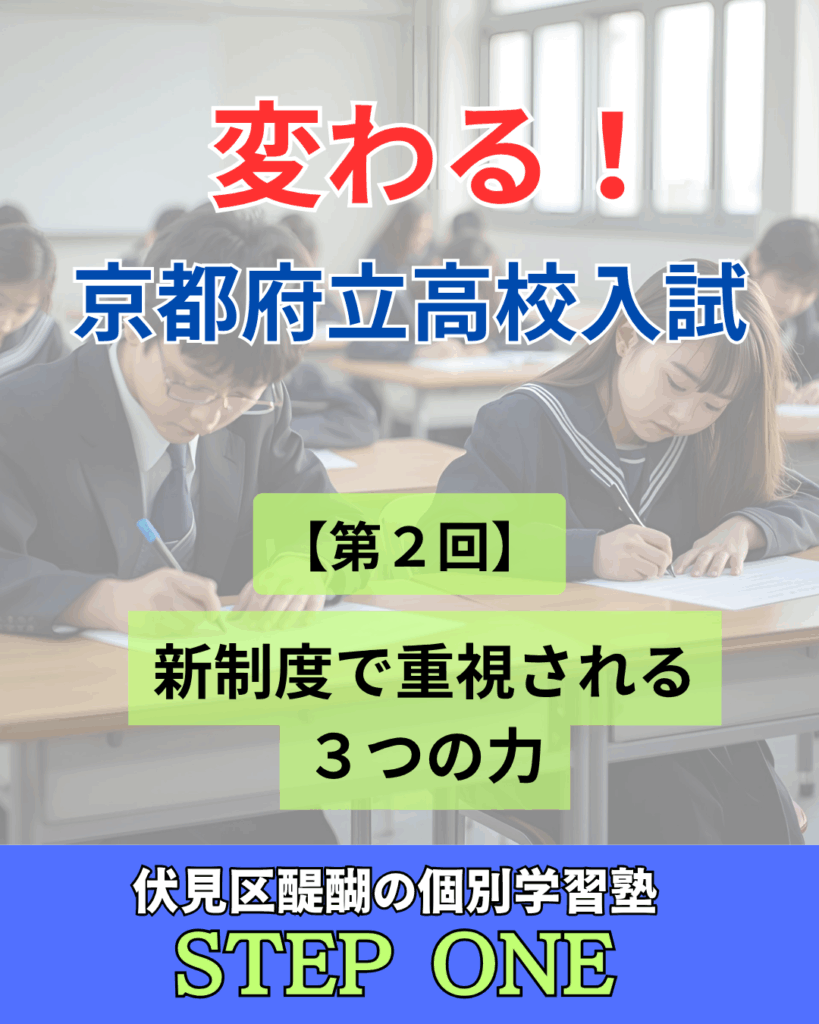いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。
前回は、令和9年度から大きく変わる京都府立高校入試の概要についてお伝えしました。
今回は、その中でも特に重要な「評価の中身」、つまり新制度で“どんな力”が求められるのかを、3つの視点からわかりやすくご紹介します。
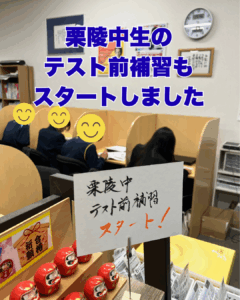
1.学力だけではない“多面的評価”へ
これまでの入試は、主に学力検査(筆記試験)と調査書(内申点)を中心に合否が決まっていました。
しかし令和9年度入試からは、学力に加えて「意欲」「思考力」「協働性」など、より多面的な評価が導入される見込みです。
学校生活全体でどんな姿勢で学び、どんな力を身につけてきたかを総合的に判断する――。
そんな時代に入るのです。
2.新制度で重視される3つの力
① 学力(基礎力+思考力)
どんな制度になっても「学力の土台」は変わりません。
定期テストで基礎を確実に積み上げることが最も重要です。
ただし今後は、「知識を使って考える力」も問われます。
たとえば国語では文章を読み取って自分の意見を書く問題、英語ではスピーキング・ライティングを意識した表現問題などが増える傾向です。
② 主体性・意欲
日々の授業や学校活動への取組み、提出物、授業中の発言なども評価対象になります。
「教えられたことをやる」ではなく、“自分から考えて動く姿勢” が大切です。
家庭では、子どもが自分で学習計画を立てたり、わからないところを自ら質問したりするよう促すと良いでしょう。
③ 協働性・探究活動
グループでの発表や調べ学習、ボランティア活動など、他者と協力して取り組む経験が重視されます。
自分の考えを伝える力だけでなく、他の人の意見を聞き、まとめて発表する力が求められます。
3.日常生活が“評価対象”になる時代
新制度では、これまでのように「テストの点だけ」で決まるわけではありません。
提出物や授業態度、委員会活動、地域活動など、日常の努力がしっかり評価される仕組みになります。
たとえば、夏休みの自由研究、ボランティア参加、学校での発表――これらもすべて、将来的に評価につながる可能性があります。
つまり「いつかのために頑張る」ではなく、「今の積み重ねが未来をつくる」のです。
4.保護者ができるサポート
- 日々の頑張りを認めてあげる
「できたこと」を言葉にしてほめることで、子どもの意欲はぐんと伸びます。 - 話を聞く時間をつくる
活動内容を親子で話すことが、“自己表現の練習”になります。 - 取り組みを記録する
ノートやファイルに「活動メモ」を残しておくと、後の面接や作文にも役立ちます。
まとめ
新制度は「学力だけでなく、努力や意欲も見てくれる」仕組みです。
不安に思う必要はありません。むしろ、日常を大切にできる子が伸びるチャンスです。
STEP ONEでは、定期テスト対策はもちろん、「考える力」「表現する力」を育てる個別指導を行っています。新しい入試制度に向けて、今から少しずつ準備を始めましょう。
効果的な学習法や新制度への対応について詳しく知りたい方は、
👉 STEP ONEにお問い合わせください。
次回は、「現・中2から動き出そう!――学年別に見る“新入試への準備ステップ”」をお届けします。